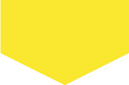リチウムイオン電池とは?種類や仕組み、主な用途や安全性も解説
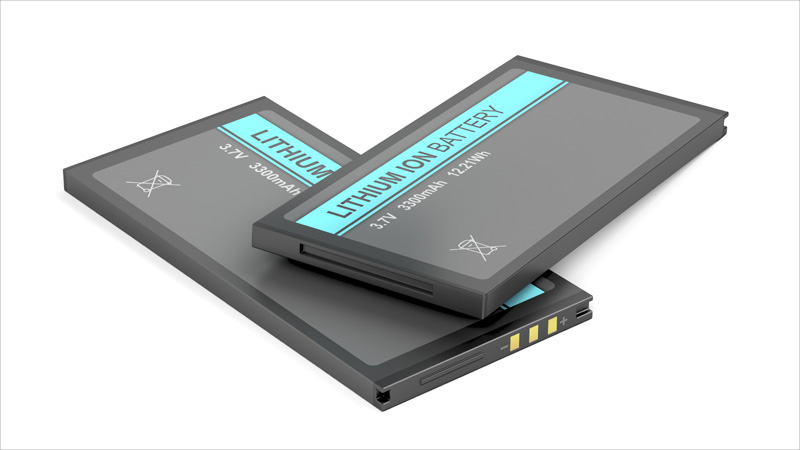
リチウムイオン電池は身の回りの家電製品に使われており、日々の生活を支えるものです。電気自動車や再生可能エネルギーなどにもリチウムイオン電池が利用されており、今後ますます社会における必要性の高まりが予想されています。
この記事では、リチウムイオン電池の概要や種類、仕組みなどを解説します。ぜひ参考にしてください。
目次 [閉じる]
リチウムイオン電池とは
リチウムイオン電池とは、リチウムイオンが電解液の中の正極と負極の間を移動して、充電や放電を行う電池のことです。小型かつ耐久性に優れた特徴があるため、スマートフォンやパソコンなどの家電製品に使われています。大容量の電力を蓄えられることで、電気自動車やインフラなどにも使用されています。
2019年、リチウムイオン電池の開発に貢献した吉野彰氏をはじめとした、3人の物理学者がノーベル化学賞を受賞しました。リチウムイオン電池は人々の生活を大きく変えた実績から、国際的に社会貢献を認められたものといえます。
リチウムイオン電池と他の電池の違い
リチウムイオン電池と他の電池は、充電可能かどうかの違いがあります。使い切りの電池は「一次電池」と呼ばれており、アルカリ電池やマンガン電池が該当します。リチウムイオン電池は、充電が可能な「二次電池」です。乾電池の2倍の電圧に対応できるため、航空宇宙分野や軍用などの多くの産業で利用されています。
リチウムイオン電池の種類
リチウムイオン電池には、以下のような種類があります。
- ニッケル系:高容量だが、ショートなど安全面に問題がある
- マンガン系:安全性が高く、車載用電池として利用されている
- コバルト系:容量は少ないが、価格が低い
- チタン酸系:急速充電できるが、エネルギー密度が低い
それぞれ違った特徴があり、異なる用途での利用が可能です。リチウムイオン電池の種類については、こちらの記事で詳しく解説します。
参考記事:リチウムイオン電池の種類~それぞれの特徴や安全性、用途などを解説
リチウムイオン電池の仕組み
リチウムイオン電池は、正極と負極、電解液で構成されているものです。正極と負極は接触しないように、セパレータで仕切られています。
リチウムイオン電池の充電は、正極側にあるリチウムイオンが電解液を通して負極側に移動し、電位差が生じることで電気を作ります。放電は、外部の回路を通って負極側にあるリチウムイオンが正極側に移動し、電気エネルギーを放出する仕組みです。
参考記事:リチウムイオン電池の仕組みとは?長持ちさせる方法も解説
リチウムイオン電池の材料
リチウムイオン電池の材料は、「正極活物質」「負極活物質」「セパレータ」「電解液」です。以下で解説します。
正極活物質
正極活物質は、電池の正極で用いられる活物質です。活物質とは電気をためる物質のことです。正極活物質には、コバルト酸リチウム、ニッケル酸リチウム、マンガン酸リチウムなどが使われます。
負極活物質
負極活物質は、電池の負極に使われるものです。ほとんどの製品でリチウムイオンの吸蔵・離脱(インターカレーション)反応に適した黒鉛(グラファイト)が使用されています。
セパレータ
セパレータは、正極と負極を電気的に絶縁して電解液を保持する役割をもつ物質です。現在の主流は微細孔を有したポリオレフィン系が使用されており、ポリエチレンやポリプロピレンなどが使われます。ポリオレフィン系のセパレータは温度が上がると溶けて孔をふさぐシャットダウン機能を持っています。
電解液
電解液はリチウムイオンを移動させるものです。酸化分解電位の高い炭酸エステル系溶媒が使われており、環状カーボネートの炭酸エチレン、炭酸プロピレンなどがあります。
リチウムイオン電池の用途
リチウムイオン電池には電気自動車やスマートフォンなど、さまざまな用途があります。以下で解説します。
電気自動車

電気自動車には、リチウムイオン電池を使った蓄電池が利用されています。リチウムイオン電池の性能は高く、大型のリチウムイオン電池の開発や実用化も進行中です。電気自動車だけでなく、電動自転車や電動バイクなどにも応用されており、電気自動車の普及に向けて多くの企業が価格や技術で競争しています。
参考記事:電気自動車の導入が進む背景とは?メリット・デメリットについても解説
参考記事:EV(電気自動車)とは?HVとの違いやメリット・デメリット、選び方なども解説
スマートフォン・パソコン

リチウムイオン電池は小型軽量化、長寿命化に成功したため、スマートフォンやパソコンなどに使われています。現在はスマートフォン自体の性能が良くなり、消費電力を抑えることが可能になりました。1回の充電で電力が長持ちするので、省電力で長時間の稼働ができます。リチウムイオン電池には有害な物質を使っていないため、多くの電子機器で採用されています。
エネルギー設備

リチウムイオン電池は、太陽光発電や風量発電などの再生可能エネルギーの出力が安定しないといった、問題の解決に役立つものです。再生可能エネルギーは季節や環境などによって供給量が変動するため、リチウムイオン電池がエネルギー出力の不安定さを補います。リチウムイオン電池のコストが下がる場合、系統安定化用電池の主流になることが予想されます。
リチウムイオン電池が発火する原因
リチウムイオン電池が発火する原因は、リチウムの漏出やガスによる膨張です。以下で、解説します。
リチウムが漏れる
電池容量が低下して電池の劣化が進行すると、内部のリチウムが漏れる「析出」が発生するリスクが高まります。電池からリチウムが漏れると、内部短絡や発火を引き起こす危険性が高まるため、長期間の使用には注意が必要です。
ガスが発生して膨張する

リチウムイオン電池は長期間の使用や放置状態が続くと、内部でガスが発生しやすくなります。ガスによって内部の構造にズレが生じ、衝撃が加わることで正極と負極が触れて引火する危険性を高めます。電池の内部にガスがたまると大きく膨らみ、発火や破裂などのリスクがあるため注意しましょう。
リチウムイオン電池を安全に使用するには
スマートフォンやパソコンなどの電化製品は、充電や放電のしすぎに注意が必要です。リチウムイオン電池は周囲温度25℃を基準にしているため、高熱になる環境を避ける必要があります。高所から落としたり圧力を加えたりする場合でも発熱しやすくなります。リチウムイオン電池は衝撃を与えると破裂や発火の原因になるため、丁寧に扱うことが重要です。
リチウムイオン電池の廃棄方法
リチウムイオン電池を捨てる際は、産業廃棄物として廃棄しましょう。廃棄物処理業者に処分を委託して、安全面に配慮して廃棄します。リチウムイオン電池が適切に処理されない場合、罰則が科されるため注意が必要です。リチウムイオン電池を扱う各メーカーに問い合わせると、処分方法を教えてくれたり、処分業者を紹介してくれたりする場合があります。
リチウムイオン電池の寿命
リチウムイオンバッテリーは、約500回の充電と放電を繰り返すと寿命に近づくと言われています。バッテリーのサイクル劣化と呼ばれており、長く使うほどに充電可能な電力量が減り、使用可能な時間が短くなる現象が起こります。リチウムイオン電池は、満充電・残量0の状態で放置すると劣化が早くなるため注意しましょう。
リチウムイオン電池が搭載された機械を長期間使用しない場合、バッテリー残量が50%程度の状態を維持することが重要です。約1年半から2年経過した場合、商品の買い換えを検討しましょう。
参考記事:リチウムイオン電池の仕組みとは?長持ちさせる方法も解説
まとめ
リチウムイオン電池は小型かつ耐久性が高く、スマートフォンや自動車などの多くの機械に使用されています。使用する目的や用途はさまざまですが、使い方を間違えると発火する可能性があります。リチウムイオン電池は安全な使い方や寿命、廃棄方法を把握したうえで使用することが重要です。
参考記事:リチウムイオン電池の種類~それぞれの特徴や安全性、用途などを解説
吉田SKTは表面処理、テフロン™フッ素樹脂コーティングの専門メーカーです。当社の技術はリチウムイオン電池製造の際に発生するお悩みを解決した実績がございます。下記の事例をご覧いただき、同様の件でお困りの際はぜひ一度お問合せください。改善策をご提案いたします。